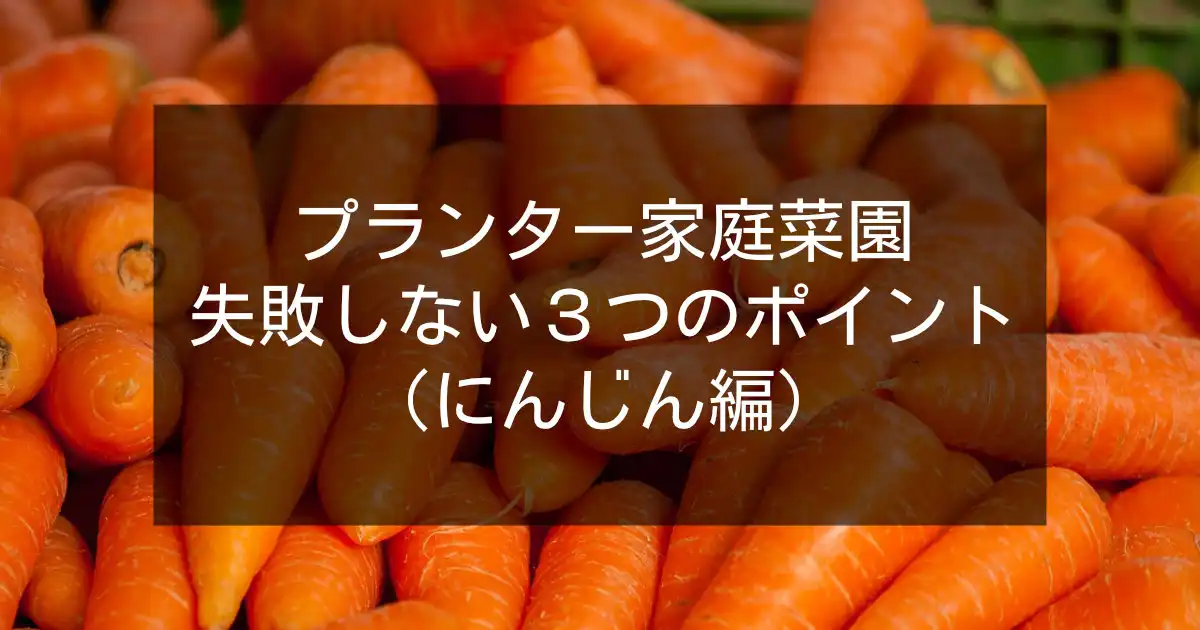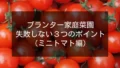「家庭菜園を始めたいけど、何が必要で何から始めればいいかわからない」
「家庭菜園を始めたいけど、うまくできるか心配」
「家庭菜園に興味があるけど、畑を持っていない」
こんなお悩みを抱えている方はいませんか?
知識0からでも大丈夫!
畑を持ってなくても大丈夫!
JAで農業振興に6年間従事した元営農指導員が、誰でも簡単に始められる家庭菜園についてお伝えします。
それは、プランターを使ったベランダでできる家庭菜園です。
限られたスペースなので、たくさんの野菜を育てることは難しいですが、その代わりに管理がしやすいメリットがあります。
例えば、野菜栽培は土づくりが重要になります。
野菜栽培には、水はけのいい土が適しています。また、土壌酸度の調整も重要です。
土づくりに失敗したら、その時点でうまく栽培することはかなり難しくなります。
しかし、プランター栽培では市販の培養土を使用することで、土づくりの段階での失敗はありません。
初心者の方でもプランター栽培にすれば、失敗するリスクを軽減することができます!
ベランダでの家庭菜園は、新鮮な野菜を手軽に育てることができる素敵な方法です。
にんじんは、プランター栽培に適した野菜の一つです。
この記事では、ベランダでにんじんが失敗しないための3つのポイントと栽培方法をお伝えします。
ぜひ、参考にして家庭菜園を楽しんでください。
1、初心者が失敗しないための3つのポイント

筆者が考える、初心者の方が失敗しないために押さえていただきたいポイントは下記の3つになります
①適切なプランターを選ぶ
②日光と水管理
③種まきと間引き
では、それぞれ細かく解説していきます。
Point1 適切なプランターを選ぶ
サイズと深さ
にんじんは深い土が必要なため、幅20cm以上・深さ30cm以上のプランターを選びましょう。根が伸びやすく、太く長いにんじんを育てるためにはスペースが重要です。
排水の良さ
プランターには底面に十分な数の穴が開いていることを確認しましょう。また、排水性の良い培養土を使用することで、根の腐敗を防ぐことができます。
Point2 日光と水の管理
日光の確保
にんじんは日照量が豊富な場所で育つため、ベランダでの栽培でも日中に直射日光を浴びる場所を選びましょう。日照時間が限られる場合は、移動可能なプランターを使用して、日光を最大限に取り入れる工夫をしましょう。
水の管理
にんじんは乾燥に強い野菜ですが、適度な水分を与えることも重要です。土の表面が乾いたら水やりを行い、土の湿度を適切に保ちましょう。水やりの頻度は気温や季節によって異なりますが、基本的には週に1~2回程度、土が乾いたらたっぷりと水を与えると良いでしょう。
Point3 種まきと間引き
種まきのタイミング
春から夏にかけて種まきができます。種まきは春が最適ですが、適切な温度と湿度を保つことが重要です。種まき前にはプランターに培養土をしっかりと準備し、種を均等にまくようにしましょう。
間引きの重要性
種まき後、2回の間引きを行いましょう。間引きによって苗の間隔を広げ、健康的な成長を促すことができます。間引くことで根がゆとりを持ち、太く立派なにんじんが育ちます。
2、準備するもの

- プランター
- 培養土
- じょうろ
- にんじんの種
- 追肥用の肥料
プランターは上記の通り幅20cm以上・深さ30cm以上のものを準備してください。
鉢底石は洗って、繰り返し利用できるので、ネットに入っているものがおすすめです。
培養土を選ぶ際のポイントは、「有機肥料が入っている物を選ぶ」 「酸度調整してある物を選ぶ」ことです。おそらく、ほとんどの培養土が酸度調整がしてあると思いますが、念の為確認をしておきましょう。
プランター栽培では5寸にんじん、3寸にんじん、ミニにんじんの種がおすすめです。
種の袋の裏側に地域・種まき時期・収穫時期が記載されています。
お住まいの地域で、春から夏に種まきできるものを選んでください。
地域が地図ではなく、「冷涼地」「中間地」「暖地」で表記されている場合があります。
よくホームセンターで販売されている種を取り扱っている「株式会社トーホク」さんに問い合わせたところ
中間地→関東地域
冷涼地→関東よりも北の地域
暖地→関東よりも西の地域
ただし、山間地は冷涼地になる場合もあるとのことでした。
各メーカーさんで違いがあるので、「株式会社トーホク」さんの種を使う場合の目安にしてください。
追肥用の肥料は、固形の化成肥料がおすすめです。水やりの際に成分がじわじわ溶けて長い期間で効果があります。
3、種まき作業
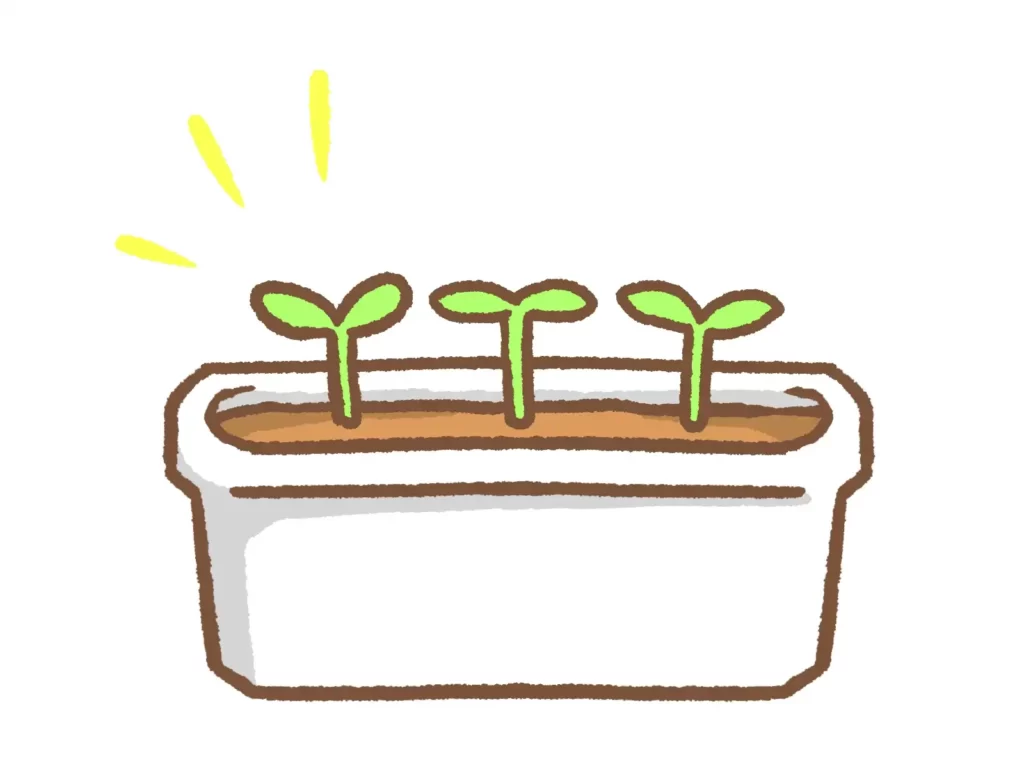
1.プランターの底に鉢底石を敷き詰める
2.先ほど、敷き詰めた鉢底石の上に培養土を入れる
プランターいっぱいに培養土を入れるのではなく、上に3cm~5cmくらいの余裕を持たせてください。水やりをする際に溢れるのを防ぐためです。
3.種をまくための溝を作る
溝と溝の間隔(条間)は10cm~15cm、深さは5mm程度にしてください。
ニンジンの種は発芽するのに光が必要(好光性)です。
溝が深すぎると、発芽不良の原因になります。
4.種まき
種と種の間が2mm~3mmになるようにスジまきをします。
種と種が重ならないようにすれば大丈夫です。
5.覆土
種をまいた溝に土を被せます。
溝が埋まる程度にしてください。覆土が厚いと発芽不良の原因になります。
被せた後に、種と土を密着させるために手で軽く抑えてあげます
4、栽培中の管理

水管理
発芽までは土が乾燥しないように注意しましょう。
もし、くん炭・切りワラ・腐葉土があれば覆土の上に薄くまくといいでしょう。
発芽後は土の表面が乾いたら水やりを行い、土の湿度を適切に保ちましょう。水やりの頻度は気温や季節によって異なりますが、基本的には週に1~2回程度、土が乾いたらたっぷりと水を与えると良いでしょう。
間引き
間引きは2回行います。健全な苗を残して指で摘み取ります。苗が密集しているとニンジンの根は太く生長できません。しっかりと間引きをして十分な株間を取るようにしましょう。
1回目は本葉が2~3枚の時に、株間が2~3cm程度になるように間引きを行います。
間引いた葉は食べることができます。
2回目は本葉が5~6枚の時に、株間が10cm程度になるように間引きを行います。
追肥
2回目の間引きのタイミングで100㎠あたり5~10g程度を与えましょう。
株の間にまいて軽く土に馴染ませてください。
追肥のやり過ぎには注意してください。
土よせ
にんじんが成長すると根の肩の部分が土の上に見えるようになります。
土よせは間引き後の転倒防止と、根が太くなっていく時に肩の部分が出ていると緑色になってしまうのを防ぐ効果があります。
肩の部分が隠れる程度に土よせをしましょう。
5、収穫
3寸にんじん→種まき後100日
5寸にんじん→種まき後110~120日
ミニにんじん→種まき後60~80日
品種によって異なりますが、収穫までのおおよその目安です。
種の袋に収穫までの日数が書いてあるものがありますので、参考にしてください。
葉を摘み上げてにんじんを引き抜く際には、根元から優しく引くことで破損を防ぎましょう。
保存方法
収穫したにんじんを長く新鮮な状態で保存するためには、以下のポイントに注意しましょう。
収穫後は土や余分な葉を取り除き、水洗いして乾燥させます。
にんじんは冷暗所で保存するのが理想的です。
湿度が高いと腐りやすくなるため、湿気の少ない場所を選びましょう。
袋や保存容器に入れる前に、にんじん同士が触れないように注意しましょう。
互いにぶつかることで傷つきやすくなります。
長期保存をする場合は、冷蔵庫の野菜室や地下室などの涼しい場所を利用し、風通しの良い環境を確保しましょう。
6、病害虫
ダニ・アブラムシ
害虫の発生を防ぐため、プランター周辺を清潔に保ち、害虫の侵入経路を遮断しましょう。
必要に応じて天然の防虫剤やバリアを使用することも考慮しましょう。
黒葉枯病
黒褐色の小はん点が発生し、後にそれが大きくなり、病気になった葉の縁が上側に巻き込んで枯れる症状が出ます。
土壌を乾燥させすぎない、肥料切れさせないことに注意してください。
その他にも、葉が黄色く変色したり、斑点が現れたりした場合は、病気の可能性があります。
定期的な観察と早期発見が重要です。
必要に応じて農薬の使用を検討しましょう。
7、まとめ
ベランダでのにんじん栽培は初心者にも挑戦しやすく、美味しい自家製のにんじんを楽しむことができます。以下に、まとめのポイントをご紹介します。
- 適切なプランターを選び、深さと広さに注意しましょう。にんじんは深い土とスペースを必要とします。
- 日光と水の管理を行いましょう。十分な日光を浴びる場所を選び、適度な水やりを行いましょう。
- 種まきと間引きを適切に行い、苗の健康な成長を促しましょう。
- 有機肥料を使用し、追肥を行いにんじんの栄養を補給しましょう。
- 病害虫に対して予防策を講じ、定期的な観察を行いましょう。
- 収穫のタイミングを見極め、適切な保存方法で新鮮なにんじんを楽しみましょう。
ベランダでの家庭菜園は、手軽に楽しむことができます。
にんじん栽培を通じて、自然の恵みを味わい、自家製の健康的な野菜を収穫する喜びを体験しましょう。
初めてのにんじん栽培に挑戦してみてください。
成功したときの充実感と満足感は格別です。
是非、ベランダでの家庭菜園を楽しんでください!